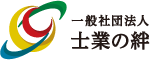遺留分侵害額請求の時効は何年?成立させない方法は?
遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、相続人が遺産を相続する際に最低限主張できる取り分のことをいいます。
自己の遺留分を侵害された相続人は、他の相続人が自己の遺留分を侵害して相続をしている場合、侵害者に対して遺留分侵害額請求を行うことにより、遺留分に相当する遺産を取り戻すことができます。
ただし、遺留分について定めている民法1042条は、相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹については遺留分を認めていません。
そのため、これらの方は遺留分侵害額請求を行うことはできません。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求権には時効が存在します。
具体的には、
①相続が開始されたことと遺留分に対する侵害を知った時から1年
②相続が開始された時から10年
のいずれかを経過すると遺留分侵害額請求権を行使することができなくなります。
このうち、①について、「侵害を知った」に当たるためには、遺留分に対する具体的な侵害について把握していることが必要となります。
なお、②について、相続は被相続人が死亡した日に開始しますが、このことについて相続人の方が認識しないまま10年が経過した場合であっても、遺留分侵害額請求権は行使することができなくなりますので注意が必要です。
遺留分侵害額請求の時効を成立させないためには
遺留分侵害額請求の時効を成立させないためには、時効が完成する前に、遺留分侵害者に対して遺留分侵害額を請求する旨の意思表示をすることが有効です。
のちのトラブルを避けるため、この意思表示は内容証明郵便によって行うことをおすすめいたします。
なお、時効完成前に一度でも遺留分侵害額請求の意思表示を行っていれば遺留分侵害額請求権自体に時効が成立することはなくなります。
しかし、遺留分侵害額請求権の行使によって発生した金銭支払い請求権などの債権は、通常の債権と同様、別個に消滅時効が成立するため、遺留分侵害額請求権の行使後もすみやかに債権回収を行うことをおすすめいたします。
相続に関するご相談は一般社団法人士業の絆におまかせください
今回は、遺留分侵害額請求について解説していきました。
一般社団法人士業の絆では、相続に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
コンプライアンス...
近年は、事業や経営において強くコンプライアンスの遵守が求められています。 例えば、株式会社の取締役は […]

-
社名やロゴなどの...
商標権とは商標権とは、商品またはサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権のことをいいます。商標 […]

-
生前対策の重要性...
生前対策とは、ご自身の死後に発生する財産の相続に備えて自分が亡くなる前から様々な制度を活用して対策をしておくこ […]

-
遺産分割協議と協...
遺産分割協議とは、被相続人の法定相続人が複数いる場合、つまり共同相続の場合に、相続人間で共有状態となっている遺 […]

-
節税対策
節税対策にはさまざまな方法がありますが、「脱税」と判断されないように慎重に行う必要があります。 会社 […]

-
相続登記(不動産...
相続登記とは、相続を原因とする所有権移転登記のことを言います。相続登記をするには被相続人が所有し、被相続人名義 […]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
法人情報
Overview
| 名称 | 一般社団法人 士業の絆 |
|---|---|
| 代表理事 | 小笠原 哲二 |
| 所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
| Tel | 0120-301-515 |
|---|---|
| kizuna@shigyo-k.com | |
| 設立 | 2020年4月13日 |